2022年7月15日
ちょこっと音楽理論 ダイアトニックコードその3
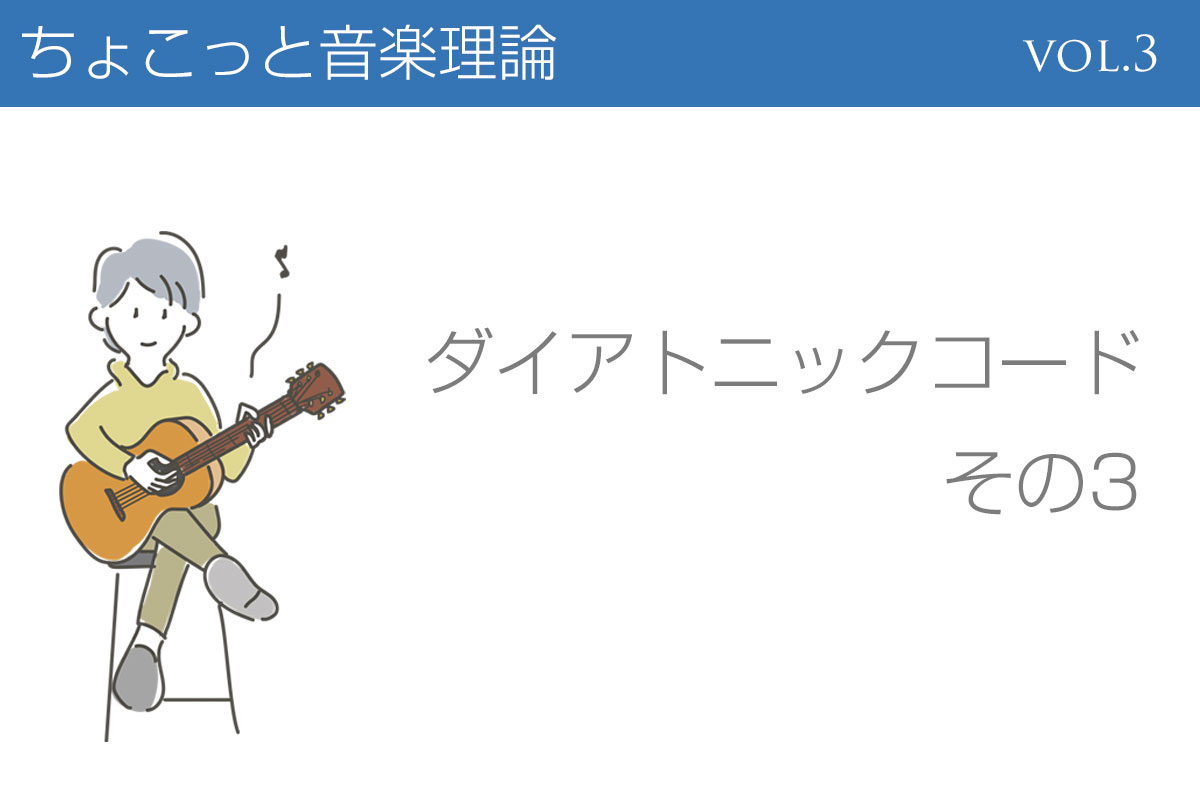
過去の記事はこちらから。
ディグリーネーム
前回まででCメジャースケールのダイアトニックコードを説明しました。
主音(1度)、3度、5度、7度で4つの和音とし、主音からの位置関係でコード名が決まるという話でした。
下の画像がCメジャースケールのダイアトニックコードです。
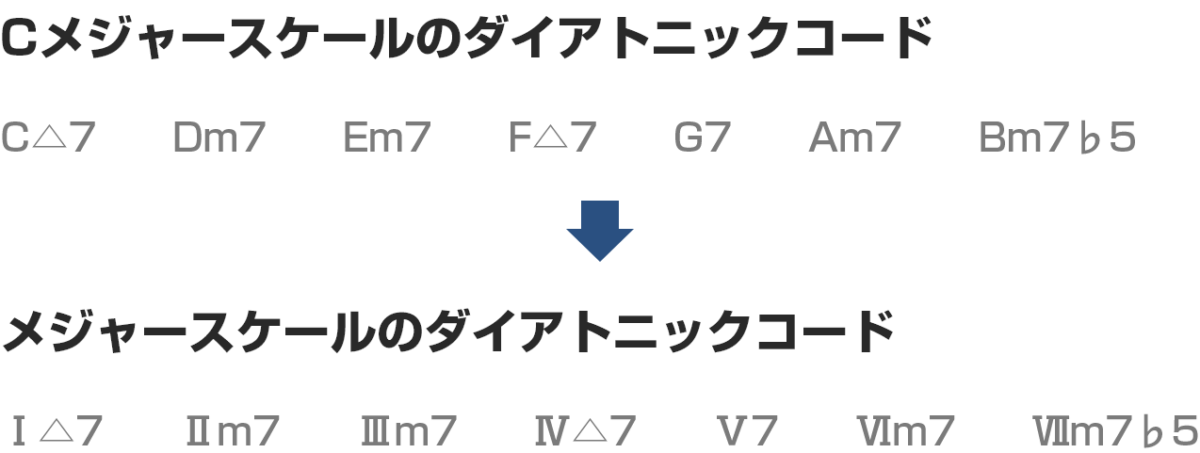
Cメジャースケールにおけるダイアトニックコードの種類は、Cだけでなくすべてのメジャースケールで同じになります。
上図のようにⅠ△7のように表します。ローマ数字は度数を表しています。
このように度数によるコード表示のことをディグリーネームといいます。
ディグリーネームを使うと、スケールの1~7度の音を把握していると、すぐにコードがわかるというものです。
これはメジャースケールはメジャースケールのディグリーネームがありますが、マイナースケールにも同様にディグリーネームがあります。
スケールについて
メジャースケールのディグリーネームを活用して、Cメジャースケール以外のメジャースケールとそのダイアトニックコードを見てみます。
このためにはスケールについての知識が必要になりますので、簡単に説明します。
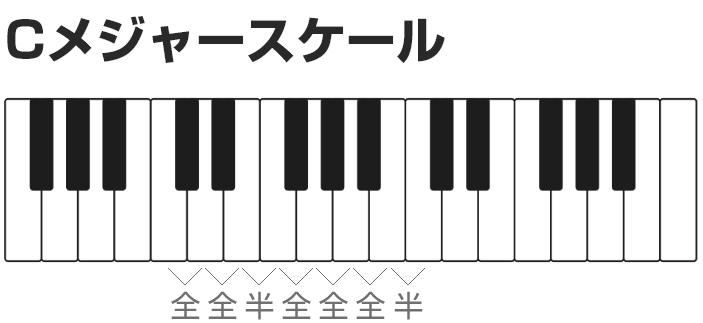
Cメジャースケールは一番始めに説明したとおり「ドレミファソラシド」です。
この時大切なのはやはり位置関係です。1度から2度、2度から3度と言った7つプラス1オクターブ上のド(1度)までの位置です。
メジャースケールは上図のようにド~ドまでが
全音(黒鍵あり)
全音(黒鍵あり)
半音(黒鍵なし)
全音(黒鍵あり)
全音(黒鍵あり)
全音(黒鍵あり)
半音(黒鍵なし)
となっていますので「全全半全全全半」と言います。
他の音を主音にした時も、同じ位置関係の鍵盤を押さえればメジャースケールになります。
レ(D)を主音にしたときのメジャースケールが下図になります。
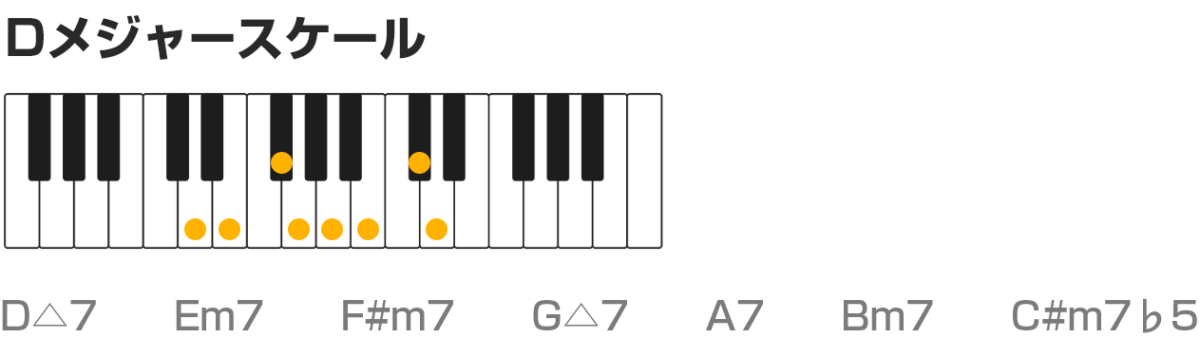
そして、ディグリーネームにそってコードを入れると上のようなダイアトニックコードになるということです。
トライアド
ダイアトニックコードはこれまで4つの和音で説明しましたが、トライアド(3和音)という考え方もあります。
これは単純に7度の音を省いて和音を形成する方法です。
こちらのほうが簡単ではありますが、ダイアトニックコードの仕組みをトライアドだけで覚えると、他の理論との連動に欠ける部分が多くなるので、あくまで簡易版くらいで覚えたほうがいいと思います。
また、トライアドで出てくるコードは、もちろんそのまま作曲で使うこともできます。つまりド(C)を主音としたメジャースケールの曲の場合、
C△7、Dm7、Em7、F△7、G7、Am7、Bm7♭5
以外に
C、Dm、Em、F、G、Am、Bm♭5
のコード進行で曲を作っても違和感がないということです。
下の図はCとDのメジャースケールにおけるダイアトニックコードのトライアドです。
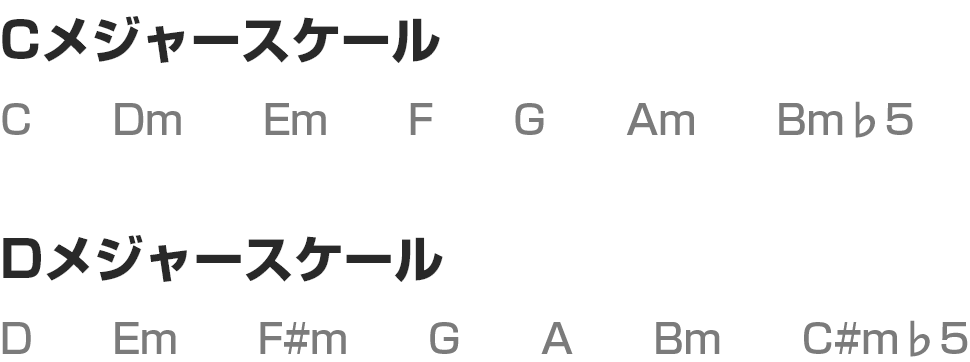
今回はここまでです。
次回でダイアトニックコードは最後になります。
概念や仕組みについてはすべて書いたので、最後にマイナースケールのダイアトニックコードについて記述して終了です。
コメントを書く